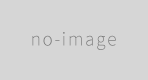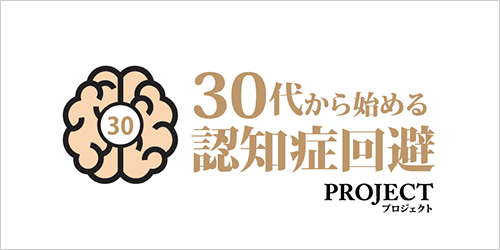ビタミンDの有効性に注目が集まっていますね![]()
今までのブログでもビタミンDについて何度か取り上げており、ビタミンDは糖尿病、筋肉増強、認知症、がんなどに対して効果があると期待されています![]()
・【論文紹介】ビタミンD不足で糖尿病?
・【論文紹介】ビタミンD不足は認知症になりやすい
・【論文紹介】ビタミンDで乳児の筋肉量アップ
・【論文紹介】血中ビタミンD濃度が高いと乳がん生存率が高い
今回は、「ビタミンDと腸内細菌とメタボリックシンドローム」について調べている論文をご紹介します![]()
ビタミンDで腸内細菌とメタボを改善
「ビタミンDを余分に摂ることで腸内環境が改善し、メタボリックシンドロームを防ぐことができるかもしれない」という内容の、アメリカにあるシーダーズ・サイナイ・メディカルセンターなどからの動物を用いた研究報告です![]()
目的
メタボリックシンドロームは世界的に増加しており、非アルコール性脂肪肝疾患や2型糖尿病(インスリン抵抗性)などと原因が共通なことが多い。
非アルコール性脂肪肝疾患は長期的な肝臓の炎症が、インスリン抵抗性は高血糖、脂質異常症、高インスリン血症のような全身の代謝性合併症が根底にあり、慢性的な軽度の炎症は非アルコール性脂肪肝疾患やインスリン抵抗性の促進と関連するという報告がある。
また、腸内細菌の乱れによって生じる腸内毒素症は軽度の全身性炎症を引き起こし、インスリン抵抗性や肝脂肪変性、メタボリックシンドロームの原因となる可能性が示唆されている。
一方で世界的にビタミンDの欠乏や不足が起こっており、ビタミンD不足と自己免疫疾患、肝炎、がんとの関連が指摘されている。
高脂肪で高カロリーな食事はインスリン抵抗性や非アルコール性脂肪肝疾患、メタボリックシンドロームの主要な原因のひとつであり、動物実験においては、ビタミンDが欠乏した高脂肪食をマウスに食べさせたところ、インスリン抵抗性や肝脂肪変性が見られている。
そこで、ビタミンDと腸内細菌とメタボリックシンドロームとの関係について調べる。
方法
マウスを4群に分けて以下の食事を与え、体重増加や血液、肝臓、膵臓、脂肪、回腸、腸内細菌などについて調べた。
また、耐糖能やインスリン抵抗性などについても調べた。
①ビタミンD食:体重1㎏あたり1,000IUのビタミンDが入ったコントロール食
②ビタミンD無食:ビタミンDが入っていていないコントロール食
③高脂肪+ビタミンD食:高脂肪食(脂肪量が総エネルギーの60%)で体重1㎏あたり1,000IUのビタミンDが入った食事
④高脂肪+ビタミンD無食:高脂肪食でビタミンDが入っていていない食事
結果
・高脂肪+ビタミンD無食では肝脂肪変性が悪化し、有意に耐糖能異常やインスリン抵抗性が現れ、総コレステロールやLDLコレステロール値も高かった。
・高脂肪+ビタミンD無食では有意に血中の炎症性の物質が増加し、全身性の炎症が悪化した。
・血中のエンドトキシンの上昇と腸管透過性の増加に相関性が見られたが、ビタミンDによって血中のエンドトキシンレベルが有意に低下した。
・ビタミンD無食と高脂肪+ビタミンD無食では健康な腸内細菌叢の維持に必要な抗菌分子(ディフェンシン)の発現が有意に減少した。
・高脂肪+ビタミンD無食のマウスにデフェンシンを摂取させると腸内細菌のバランスや肝臓の炎症が改善し、血糖値や中性脂肪、LDLコレステロールが低下した。
まとめ
高脂肪食のみではメタボリックシンドロームに至らなくても、高脂肪食を摂ることにビタミンD欠乏症が加わると腸内環境が悪化してメタボリックシンドロームを引き起す可能性がある。
<論文>
Vitamin D Signaling through Induction of Paneth Cell Defensins Maintains Gut Microbiota and Improves Metabolic Disorders and Hepatic Steatosis in Animal Models
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=27895587)
まとめ
これは動物実験による結果なので、私たちヒトにそのまま当てはめることはできませんが、現代人は「夜型の生活」、「紫外線を避ける」、「ビタミンDが豊富な食品(魚介類、キノコ類など)の摂取量が少ない」などの影響でビタミンDが不足している人が多いと言われています![]()
ビタミンDは日光(紫外線)に当たることで体内で作ることができる栄養素であり、どれくらい日に当たるとどの程度のビタミンDが作られるのかなどは以前のブログでまとめているため参考にしてみてください
→【論文紹介】血中ビタミンD濃度が高いと乳がん生存率が高い
ビタミンは欠乏すると健康を維持できず、命に関わります![]()
健康の維持、増進のためには、厚生労働省の定める目安量(成人男女:5.5μg/日)よりも多めに摂る方が良いと考えられるため、「日焼け止めなどを付けずに日光に当たる」、「魚介類やキノコ類を食事に多く取り入れる」、「サプリメントを活用する」などできることから生活に取り入れてみてはいかがでしょうか![]()

(さ)
http://www.nutritio.net/linkdediet/news/FMPro?-db=NEWS.fp5&-Format=detail_news.htm&kibanID=58002&-lay=lay&-Find
日本人の食事摂取基準2015年版