
本日12月13日はビタミンの日です!
ビタミンの日は「ビタミンB1(オリザニン)」の発見者として知られる鈴木梅太郎氏を顕彰し、ビタミンの知識の普及に寄与する情報発信活動を行っていくことを目指し、当時の学会(東京化学会例会、1910年 12月13日)で発表された日にちなんで制定されました。
そこで今回はビタミンの日にちなんで「ビタミンB1」についてまとめます。
目次
脚気とビタミンB1の歴史
脚気は精白米が広がった江戸時代から明治時代にかけて全国で流行し、重症化すると死をもたらすため、国民病として恐れられてきました。しかし、研究が進み鈴木氏が米ぬかから脚気を防ぐ有効成分を抽出する事に成功した事で、その研究は飛躍的に進みました。
当時、鈴木氏はこの物質を「アベリ酸(後にオリザニンに改名)」と命名し、1910年12月13日に東京化学会で第一報を報告、翌1911年1月の東京化学会誌に論文を掲載しましたが、その後この物質の発見を競ったポーランド人のフンクが提唱した「Vitamin(e)」という名称が採用され、1927年に「ビタミンB1」と命名されました。
物質の発見自体は鈴木氏の方が早かったと言われており、ビタミンB1の最初の発見者だとされています。
ビタミンB1の働きと不足による症状
ビタミンB1は糖質を代謝するのに必要な栄養素で、糖質は脳や神経のエネルギー源となります。
そのためビタミンB1が不足すると末梢神経や筋肉への障害がおこる脚気の他、脳の中枢神経に障害をもたらすウェルニッケ脳症が現れる事があります。
脚気 <精白米(糖質)の摂取が多い日本人に多くみられる>
- 全身倦怠
- 体重低下
- 四肢の知覚障害
- 腱反射消失
- 心悸亢進
- 心拡大
ウェルニッケ脳症 <アルコールの摂取が多い西洋人に多くみられる>
- 眼球運動麻痺
- 歩行運動失調
- 意識障害
日本人のビタミンB1摂取状況
現代では脚気と診断される事は少ないため昔の病気であると思いがちですが、平成27年国民健康・栄養調査の結果によると、ビタミンB1の摂取量は男女とも全ての年代で推奨量を下回っており、ほとんどの人が欠乏を防ぐために必要な量をとれていないと考えられます。

特に以下に示す、ビタミンB1が不足が疑われる方は、この機会に意識してビタミンB1を摂取すると良いかもしれません。
ビタミンB1が不足が疑われる人
- 疲れやすい人
- アルコールを多く摂取する人
- 喫煙をする人
- 清涼飲料水やインスタント食品、お菓子をよく摂取する人
- イライラしやすい人
- 激しい肉体労働をする人
- 妊婦・授乳婦
- 甲状腺機能亢進症
ビタミンB1は豚肉やうなぎ、落花生、たらこ、玄米に多く含まれていますが、水に溶けやすく、熱に弱い性質を持っているため洗浄や調理は短時間で行い、できるだけ出来たてを食べる事をお勧めします。
また、ニンニクやネギなどに含まれるアリシンと結合すると脂溶性にかわり、熱にも強くなるため炒め物をする際などはニンニクなどと合わせて調理する事がお勧めです。


参考文献:基礎栄養学 同文書院
暮らしの栄養学 日本文芸社
平成27年国民健康・栄養調査
東京大学ホームページ 先人に学ぶ 鈴木梅太郎のビタミンB1の発見
国立健康栄養研究所 ビタミンB1解説







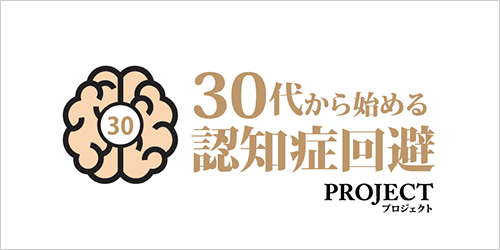



企画開発部
株式会社ヘルシーパス